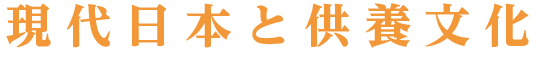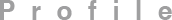2025.03.19
2025.03.19

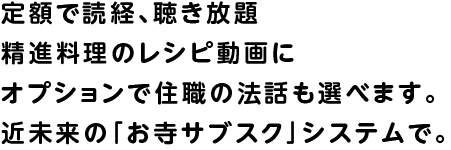
日本人にとって一番身近な仏教は、お葬式や法要の儀礼だろう。小さな子どもも大人と一緒に仏様に両手を合わせ、お盆や彼岸には菩提寺に足を運ぶ。しかし少子高齢化で墓を継承する人も減り、日本の檀家制度は危機に直面している。一方で、樹木葬や海洋散骨、宇宙葬など埋葬のしかたは多様化し、IT技術を活用したロボット導師まで登場するなど、葬儀のスタイルも変化しつつある。日本仏教の供養儀礼を研究し、曹洞宗の僧侶でもある徳野先生に、日本の供養文化とその未来についてうかがった。
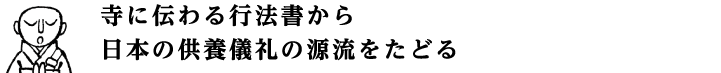 寺に伝わる行法書から
寺に伝わる行法書から
日本の供養儀礼の源流をたどる

私は仏教の供養文化、なかでも日本の禅宗における供養儀礼を中心に研究しています。じつは生家が宮城県のお寺で、小学生のときに得度しました。宗教学に興味を持ったのも、私のような地方の菩提寺の僧侶たちが、かつてどうやって仏教をひろめ、一般に根づかせていったのかに関心があったから。道元禅師のような祖師の思想も大切ですが、むしろ身近なお坊さんたちの宗教生活を知りたいと、葬儀や儀礼を中心に研究を進めてきました。
例えば、「葬式仏教」あるいは「葬祭仏教」という言葉があるように、日本の仏教は葬儀との関わりが深いのですが、供養儀礼の研究は手つかずのところも多いのです。禅宗には、僧侶が日々やるべきことや年中行事のやりかたが記された儀礼マニュアルともいうべき「清規(しんぎ)」という寺ごとの行法書があります。現存する最古の清規は1103年に宋の長蘆宗賾(ちょうろそうさく)が編纂した『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』とされますが、その中に僧侶が亡くなったときの葬儀のしかたが書かれていて、それが日本の葬儀の源流となっているのです。
日本の曹洞宗の大本山、永平寺には中世から受け継がれた『永平清規』の世界が生き続けています。私もそこで1年間、修行をしました。夜明け前に起きて坐禅を組み、朝課の読経をし、質素な粥の朝食をいただき、掃除をして昼の法要...と夜の9時まで分刻みで修行が続きます。私はこの修行で20kgも痩せました(笑)。

修行後に改めて清規を読むと、内容が手に取るように分かるようになりました。例えば「粥罷(しゅくは)」と書かれているのは「朝ご飯の後だな」といった具合。同時にそのときの空気感も蘇ります。すべての堂舎に人が割り振られ、くまなく浄めていく。寺の伽藍が人体だとすれば、雲水はその中を流れる血液となって生きている。史料が語っていることも、こうした実感を伴ってイメージできます。これは本当に大きな体験でした。
禅というものを研究者として客観的に見つつ、僧侶として内在的にも向き合うことができるのは、他の宗教学者にはない私の強みです。

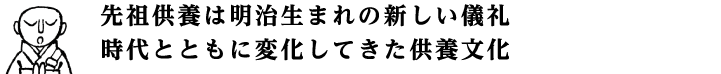 先祖供養は明治生まれの新しい儀礼
先祖供養は明治生まれの新しい儀礼
時代とともに変化してきた供養文化
清規を研究してきたなかでもっとも重要な発見は、先祖供養の儀礼が明治から始まったということです。もちろん、死者の供養そのものは、仏教の伝来当初から存在し、中世の清規にも書いてあって、以来800年続いています。しかし、儀式としての先祖供養が始まったのは近代に入ってからなんです。
日本には、皇祖神としての天照大神を奉った伊勢神宮を参拝する慣習がありました。それが、明治時代になって神道を国教に据えようとしたときに、神や先祖を国民全体で崇めるべきだという議論になり、そこに仏教界も呼応して先祖を対象とした供養の儀礼を行うようになったと考えています。

ちなみに葬儀を仏教が担い始めるのは中世からで、鎌倉時代の少し前に天台宗の僧侶、恵心僧都源信が『往生要集』や『横川首楞厳院二十五三昧起請(よかわしゅりょうごんいんにじゅうござんまいきしょう)』の中で、極楽に往生するため仏教的な功徳を積むことを重視し、臨終の作法として、仏教的な葬儀のやりかたを解説し、念仏の功徳を力説しました。それが一部の上層階級に葬儀として広がっていきます。もっとも当時は多くの民衆は野捨てが普通で、墓といっても五輪塔や板碑(石卒塔婆)という集合墓でした。


岩盤をくりぬいた中に五輪塔が納められている
その後、島原の乱以降、江戸幕府がキリスト教を禁じて人々を寺に所属させ、キリシタンではないと証明する寺請証文を発行させるようになり、それが檀家制度として根づいていきます。地方のお寺が民衆管理を担い、檀家制度を支える重要な儀礼として故人の冥福を祈る追善供養が全国に流布し、今日の仏教的な葬儀へと発展していくのです。江戸時代には四角い墓石も普及し、初期には一つだけだった戒名が、二つの戒名を刻んだ夫婦墓になり、やがて家紋が入った家の墓へと置き換わっていきます。
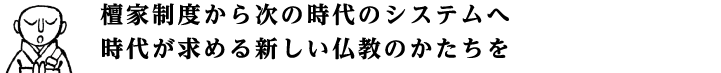 檀家制度から次の時代のシステムへ
檀家制度から次の時代のシステムへ
時代が求める新しい仏教のかたちを
いま葬儀がどんどんプライベートなものに変化していき、戒名はいらない、葬儀もいらない、埋葬も樹木葬や海洋散骨、宇宙葬など、さまざまなスタイルが登場しています。新型コロナウイルス感染症によって、昨今はオンライン葬儀も当たり前になりました。葬祭ビジネスの見本市であるエンディング産業展では、檀家制度や菩提寺にかわるものとしてITを活用したロボット導師なども提案されています。追善供養のありかたや葬儀のありかたも、さらに変わっていくでしょう。
日本は多死社会化し2040年頃にピークを迎え、その後は死者数も葬儀も減っていくといわれています。そうなると檀家制度を経済基盤としてきたお寺は立ちゆかなくなります。そのとき、改めて本当の仏教のありかた、生きている人と向き合った仏教が問われるのではないでしょうか。
そもそも、中世まではどの寺に帰依するかは自由に選択できました。禅僧の世界では、修行をしながらお寺を渡り歩いて自分の正師を捜し求め、徳のある住職には多くの修行僧が集まり、お寺の格式も決まりました。おそらく、これからは信仰したいお寺を人々が自由に選ぶ時代が再びやって来るのではないでしょうか。
例えばアメリカのサンフランシスコ禅センターのように、供養とは関係なく共同生活をして坐禅を組み、自家製パンやクスクスのサラダなど、肉や魚を使わないおしゃれな精進料理を提供する。そんな形の寺が日本でも登場するかもしれません。日本でも一般の人が出家者と共同生活して修行するお寺がありますし、永平寺でも1週間の禅修行体験などを行っています。こうした、葬式や供養儀礼以外で仏教と接する機会を用意していく必要があるでしょう。
あるいは、現代社会のシステムをまるごと仏教に置き換えていくような話もあるかもしれません。仏教のサブスクリプションに登録すると読経のコンテンツが得られたり、半年に1回、お寺の修行にエントリーできたり。高僧とZoomでつながろう、とか。
いずれにしても、これまでの寺檀関係を自明視せず、時代に適った形に刷新していけばいい。仏教は諸行無常、常に物事は変化してやまないというのが真理なのです。
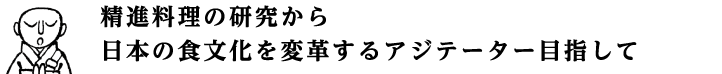 精進料理の研究から日本の食文化を変革するアジテーターを目指して
精進料理の研究から日本の食文化を変革するアジテーターを目指して
昨今は宗教社会学、宗教民俗学といった具合に学際化が進み、研究手法として宗教学の独自性を出すのは難しいのですが、私はむしろ宗教学が研究を活発化させる火付け役になればと考えています。
私が研究している精進料理も、禅や日本文化に関わる学際的なテーマです。ご存じの通り、精進料理は仏教的な菜食料理を指し、永平寺でも参拝者には「雲水は精進料理を食べている」と説明されるわけですが、雲水は精進料理とは言いません。朝は小食、昼は中食、夜は薬石と呼ばれます。
なぜかというと、精進料理という言葉は仏教的な言葉ではないからです。お釈迦様が説かれた『八正道』の教えの中に「正精進」という言葉があります。これは、正しく努力せよという意味です。一方、食に関わる事柄は「正命(しょうみょう)」、すなわち正しい生活の教えの中で説かれていて、道元禅師も「正命食」と語っています。
では「精進料理」という言葉はどこから出てきたのか。調べたところ、江戸時代の料理書の中にありました。檀家制度が広まって、法事の際にお坊様に食事を出すとき、肉や魚は食べられない。そこで仏教的な食である"精進料理"が求められた。つまり、精進料理とは法事でお坊様に出す食事の総称であり、お寺の食文化を在家の目線で語った言葉だったというわけです。
日本仏教では、明治期以降に「肉食妻帯勝手たるべし」というお触れが出てからはすっかり世俗化してしまいました。私自身、お肉が大好きで、傍から見ると戒律を守っていない俗っぽい僧に見えてしまうと忸怩たる思いもあります。これからはより僧自身の生き方が問われる時代になるはずですから、私たちも菜食の意義を発信しつつ、自分自身が変わっていくよう主体的に関わっていく必要があるでしょう。
牛丼ならぬヴィーガン丼など新たなメニューを開発したり、駒澤大学にオフィシャルの精進レストランなどを作ったりしてもおもしろいですよね。
研究活動を社会のよりよい変革、新しい変化を生み出す起爆剤として、産学連携のような形で盛り上げていきたいと考えています。

- 徳野崇行准教授
- 2011年駒澤大学大学院人文科学研究科修了。博士(仏教)。2007年から1年間、大本山永平寺に安居。2012年駒澤大学非常勤講師。2015年同大学仏教学部専任講師。2019年より現職。生家は宮城県の寺院で、小学生で得度。研究者であり曹洞宗僧侶でもある視点を活かし、とくに日本禅宗の供養儀礼、死者供養や精進料理などを研究。著書に『日本禅宗における追善供養の展開』(国書刊行会)ほか。
関連記事 - 「ラボ駅伝」カテゴリーの新着記事
 2025.03.19
2025.03.19
 2025.02.03
2025.02.03
第32区 仲田資季准教授『プラズマの渦と流れの物理と数理』
 2024.04.10
2024.04.10
第31区 近衞典子教授『上田秋成から見る近世文学』
 2024.03.05
2024.03.05