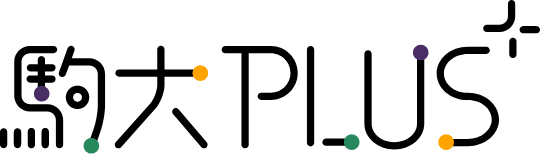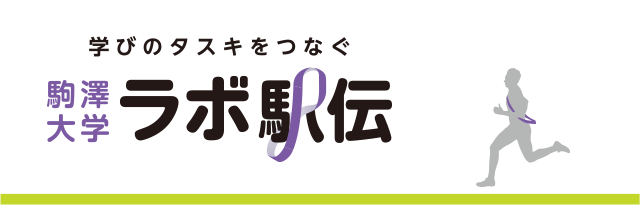2023.08.23
2023.08.23
DATE:2019.11.27研究レポート
研究こぼれ話『礼ってなんだろう?』
総合教育研究部 末次 美樹 准教授

- 総合教育研究部 末次 美樹 准教授
6歳で空手を習い始めて、今年で34年目になります。空手を始めた当初から、道場への出入りや相手と向き合った際、試合前後等々、いつでも「礼をする」ことが義務付けられていました。常に行う行為としての「礼=お辞儀」。そこにはどんな意味が存在するのだろうという長年の疑問が「礼」を研究するきっかけです。
「礼」については、儒教の経書『礼記』に詳しく解説されており、そこには実にたくさんの意味が存在していました。古代中国で成立した「礼」を簡単にまとめると、「礼」には人間関係をうまく調和する潤滑油のような作用があり、人々は古くから「礼」を用い社会の規律を正していったことがうかがえます。「礼」には、お辞儀をするという外面的なものだけではなく、人と人とが関係する空間に自身の立ち居振る舞いを合わせるというような意味も含まれています。
武道の世界には、「勝って驕らず、負けて悔やまず、常に節度ある態度を堅持する」という言葉があります。武道ではその態度を常に保つ精神力の強さが求められており、それが武道の「礼」ということになります。各種大会でも観られるように、最近では「礼」の形骸化が非常に目立ち、「礼」の体現化である形式としての「お辞儀」はするが、立ち居振る舞いは「礼」に反する選手が多くなっています。
「礼」の本質とは何か。武道の「礼」の研究をしながら、自分の日頃の行いを振り返ることが多い日々を過ごしています。
※ 本コラムは『学園通信339号』(2019年10月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。
関連記事 - 「研究レポート」カテゴリーの新着記事
 2023.08.23
2023.08.23
 2023.08.21
2023.08.21
地理空間情報の未来図―地図が導く次世代DXへの歩み―【前編】
 2022.08.04
2022.08.04
僧侶であり、歴史息づく永平寺で修行した経験を研究に活かして多彩な視点から仏教民俗学を紐解く。
 2022.06.30
2022.06.30