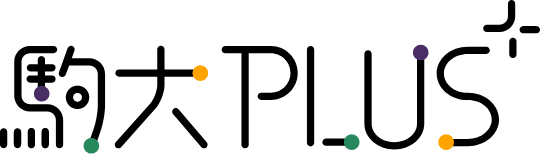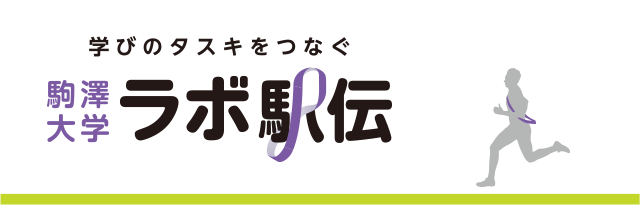2023.08.23
2023.08.23
消費者の購買行動や感性を科学的視点から読む
経営学部 若山 大樹 教授

消費者の購買行動をデータにもとづいて的確に読み解くのがマーケティングサイエンス。同時に、消費者の気分や、ワクワク・ドキドキ、五感といった感性や"あいまい"な意思決定をどのように分析し、企業の市場戦略に生かしていくかが注目されている。
企業が抱えるピンチをチャンスに変える
2014年4月から消費税が8%になりました。増税というのは本来なら商品を売る企業にとってはマイナスです。増税前は駆け込み需要で売り上げが伸びても、その後は買い控えが増えて企業にとってピンチになるからです。そんな中でも業績をアップさせているのが、しっかりとマーケティングを行っている企業です。
消費者が真に求めている製品やサービスとは何かを的確に把握し ピンチをチャンスに変える、消費者と企業の両方の期待に応える学問だといえます。
消費税増税をめぐって研究室で取り組んでいるテーマの一つが、最低価格保証に対する消費者の意識と行動です。増税は家計を圧迫しますから、これまで以上に消費者は価格に敏感になります。そこで最低価格保証制度を導入する企業への注目も高まると考えられます。スーパーや家電量販店が、他社のチラシに記載された価格の方安ければ、その価格で販売することを謳うケースですね。
すでに米国などでは盛んに行われている手法で、消費者は最低価格保証を採用しているというだけで、その店の商品がすべて安いようなイメージを持つようになり、購買意欲が高まるなどの報告もあり、日本でも研究が進んでいます。
しかし、実際に他店のチラシを提示しても条件に合わないと言われて不満を募らせたり、他人から見られる状況では日本の消費者はそういう行動を取りにくいなどの問題点も指摘されています。
白黒ハッキリの欧米人 "あいまい"さを好む日本人
私の研究室で「値切り行為」の印象を評価させたところ、日本の消費者はホンネの部分では「値切ってみたい」けれど、「人に見られるのは恥ずかしい」と考える人が多いという結果が出ました。
これをマーケティング的に見ると、値切る行為の阻害要因となっているのは「人から見られる」ということですから、誰からも見られないように工夫するなど、具体的な配慮が必要だということが見えてきます。
欧米では、どちらかというと白黒をはっきりさせる考え方で消費者のモデルやマーケティング理論が既に構築されています。それをそのまま日本に持ってきてもあいまいな判断をしがちな日本人の場合はなかなか通用しないことも多いのです。
感性工学的アプローチを取り入れたマーケティングが重要に
さて、製品やサービスに対する消費者の見方が厳しくなると、消費者の「満足」「不満足」をいかに把握するかが非常に重要になってきます。しかし、顧客アンケートで「満足している」という答えが多いからといって、その要因をさかのぼって分析しておかないと、たちまち不満足に変わってしまうことになりかねません。また、不満を持っている人が多くとも、企業がターゲットとしている層でない場合は、対応する必要はありません。アンケートをどう設計し、どう読み解くかには注意が必要なのです。
同じように判断が難しいものに、ワクワク感とかドキドキ感といった感覚的なものあります。このような、あいまいさとか感覚的なものもあります。このような、あいまいさとか感覚的なものをどのように測定・把握し、製品やサービスに応用するかを研究するのが「感性工学」で、今後ますます重要になっていくのではないかと思います。



- 経営学部 若山 大樹 教授
- 京都府生まれ。1997年東京理科大学理工学部卒。2003年筑波大学大学院社会工学研究科計量ファイナンス・マネジメント専攻修了。博士(経営学)。秋田県立大学助教、駒澤大学専任講師、同准教授を経て2016年より現職。
※ 本インタビューは『Link Vol.4』(2014年5月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものを一部変更しています。
関連記事 - 「研究レポート」カテゴリーの新着記事
 2023.08.23
2023.08.23
 2023.08.21
2023.08.21
地理空間情報の未来図―地図が導く次世代DXへの歩み―【前編】
 2022.08.04
2022.08.04
僧侶であり、歴史息づく永平寺で修行した経験を研究に活かして多彩な視点から仏教民俗学を紐解く。
 2022.06.30
2022.06.30