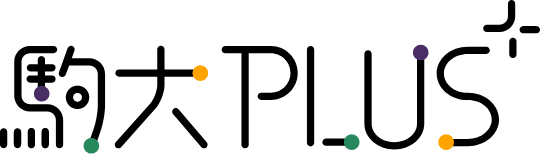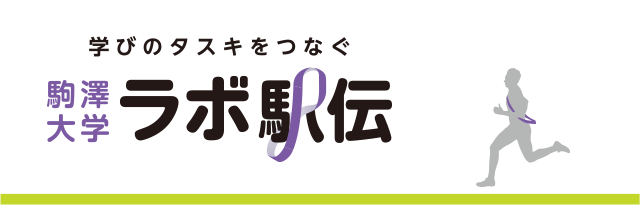2023.08.23
2023.08.23
研究こぼれ話『放射線治療人材教育センター』
医療健康科学部 保科 正夫 教授

- 医療健康科学部 保科 正夫 教授
- 研究テーマは、放射線治療技術学。
人類に投げかけられている難題である"がん"と私の関わりは、40年を超える。その中、私は放射線治療における線量評価と安全な治療のための管理を専門としてきた。現在、日本では"がん"によって毎年、約36万人の方々が亡くなられており、例えば、品川区の区民が忽然と消失しているとも云える。また、がん罹患数が約86万人/年(2012年)であることを考え合わせると、一層気持ちが萎える思いである。
大学病院を含めた一般的な病院で放射線治療に利用されている直線加速器(リニアック)が日本に導入されたのは1900年代中期、東京オリンピック当時であり、まだ、半世紀ほどの経験である。医療は"がん"に対して総合力(外科療法、化学療法、放射線療法)で、これに立ち向かってきたし、これからもそうであろう。しかし、欧米に比べ日本は放射線治療の活用が低迷している。2007年のデータによると、がん患者の放射線治療の適応は、米国66%、ドイツ60%、英国56%、一方、我が国では29%と有意に低い。対がん医療は総合力のどれ一つとして欠けてはならない。しかしながら、欧米に比して我が国における放射線療法の適用が進んでいない。要因の一つとして専門スタッフの数の不足が挙げられる。
駒澤大学で先般締結された産学連携プロジェクトである"放射線治療人材教育センター"(※)は、学部、大学院の教育だけでなく、社会への開放による日本の放射線治療技術の底上げに繋げるプロジェクトである。駒澤大学の皆さんのご理解を得ながら、このプロジェクトが少しでも先に進んでいくことを願っている。
※ 「放射線治療人材教育センター」については、以下をご覧ください。
本法人と(株)バリアンメディカルシステムズが日本初の産学連携事業による「放射線治療人材教育センター」を設立
※ 本コラムは『学園通信325号』(2017年1月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。
関連記事 - 「研究レポート」カテゴリーの新着記事
 2023.08.23
2023.08.23
 2023.08.21
2023.08.21
地理空間情報の未来図―地図が導く次世代DXへの歩み―【前編】
 2022.08.04
2022.08.04
僧侶であり、歴史息づく永平寺で修行した経験を研究に活かして多彩な視点から仏教民俗学を紐解く。
 2022.06.30
2022.06.30