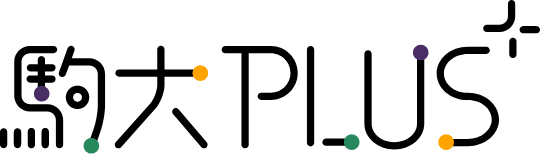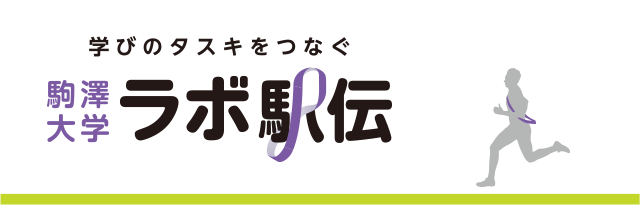2023.08.23
2023.08.23
DATE:2017.01.13研究レポート
研究こぼれ話『障害の重い子どもに学ぶ』
総合教育研究部 遠藤 司 教授

- 総合教育研究部 遠藤 司 教授
- 研究テーマは、教育心理学および障害児教育学。特に、障害の重い子どもの教育方法の研究を通して、人間の根源的生世界の在り方の解明を目指す。
障害の重い方々と教育的関わりの実践を積み重ねることにより、私は今までに多くのことを学ばせていただいた。はじめは、ほんの少し身体を動かすことや、物を見ること自体を課題としていた方々が、次第に物同士の関係や、文字や数字などの記号・概念の世界に入り、ついには、自分の考えや思いを言葉で表現するようになる姿を見てきた。
言葉を獲得するに至る過程は多様であり、それぞれの人の出す言葉も多様である。特に、初めての言葉に個性が滲み出る場合が多い。ある人は、「うきうき」と、ある人は、「たのし(たのしい)」と、またある人は「つかれた」と出した。必ずしも自由には動かない体を懸命に動かし、文字を書いたり50音表の中の文字を指したりしながら、その人らしい言葉を出す姿を見ることができた時、私は大きな喜びを感じた。「伝えたい」ということこそが、人間が言葉をもつことの1つの重要な意味であることを改めて学ぶことができた。
人間が言葉をもつことの意味は何か、「伝える・伝えられる」ことはいかにして成立するのか、40年以上言葉を出すことなく世界を生きていた人にとっての言葉の意味は何なのか。彼らがこの世に生を受け、家族の方々とともに懸命に生き、私との関わりの機会に誠実に取り組んでくれたからこそ、学び、考え、探求することができたテーマである。私にとって、このことの意味は重く深い。今後も、障害の重い方々との関わりを積み重ねることにより学びを深め、彼らの生が豊かになることにほんの少しでも貢献できれば幸いである。
※ 本コラムは『学園通信324号』(2016年10月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。
関連記事 - 「研究レポート」カテゴリーの新着記事
 2023.08.23
2023.08.23
 2023.08.21
2023.08.21
地理空間情報の未来図―地図が導く次世代DXへの歩み―【前編】
 2022.08.04
2022.08.04
僧侶であり、歴史息づく永平寺で修行した経験を研究に活かして多彩な視点から仏教民俗学を紐解く。
 2022.06.30
2022.06.30