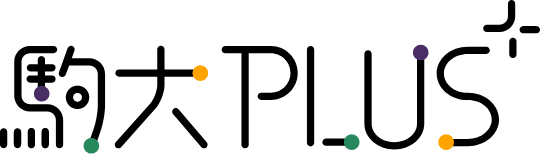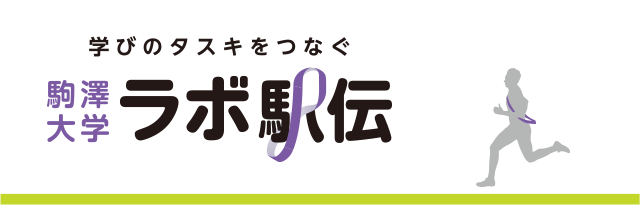2023.08.23
2023.08.23
DATE:2016.09.15研究レポート
研究こぼれ話『本との出合い』
文学部国文学科 櫻井 陽子 教授

- 文学部国文学科 櫻井 陽子 教授
- 研究テーマは日本中世文学。中でも、軍記物語を対象とする。特に平家物語を中心に、平家物語の本文流動及び受容の具体相の解明を行う。
文学研究と言えば、本を相手に部屋に引きこもるというイメージがつきまとう。決して間違ってはいないだろうが、活字以前の文学を研究している者としては、写された本の一つひとつと対面すること、そのために、手と目だけでなく、足を使うことも大切である。
50年前に定説を見た事柄に素朴な疑問を抱き、まずは先学の研究の足跡を確認しようと、福岡や京都や奈良や滋賀に赴いて、実際に同じ本を見せていただいてきた。仕事の合間を縫って、時間をかけて、少しずつ訪ねていくうちに、定説を修正することとなった。それにしても、本の博捜にかけた先学の情熱には感動するばかりである。私など表面をなぞっているだけだと思うことはしばしばである。
しかし、新出の写本はもう出ないだろうと思うのは大間違い。ある時、懇意にしている古書店の店主に、たまたま京都の古書店を紹介された。私が『平家物語』を勉強していると自己紹介をしたところ、「うちにも『平家物語』がありますよ」と何気なく言われた。天正10年6月に購入したという貼り紙がある本。江戸時代の写本は今でも世に出るが、江戸時代以前となると多くはない。調査させていただくと、私の関心にぴたりと寄り添う本であった。本との出合いはふとしたご縁から生まれるようである。
しかも、天正10(1582)年6月といえば、2日に織田信長が本能寺で暗殺されている。激動の時代を横目に、誰がこの本を手にしたのか。もし本が京都にあったのなら、本能寺の炎上を遠くから見ていたのだろうか。私まで時代に呑まれたような気がしてくるから不思議なものである。
※ 本コラムは『学園通信323号』(2016年7月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。
関連記事 - 「研究レポート」カテゴリーの新着記事
 2023.08.23
2023.08.23
 2023.08.21
2023.08.21
地理空間情報の未来図―地図が導く次世代DXへの歩み―【前編】
 2022.08.04
2022.08.04
僧侶であり、歴史息づく永平寺で修行した経験を研究に活かして多彩な視点から仏教民俗学を紐解く。
 2022.06.30
2022.06.30