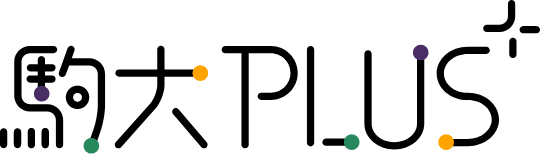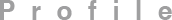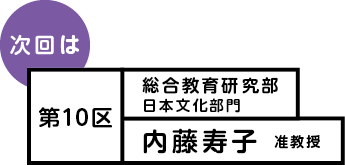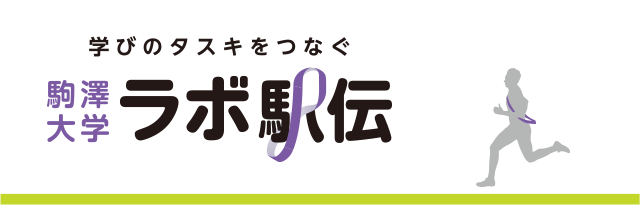2025.03.19
2025.03.19

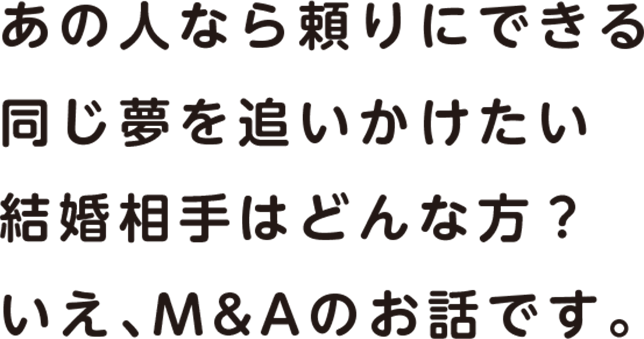
M&A(合併・買収)をマネジメントの視点から研究しているのが中村公一先生。企業買収は、すぐれた交渉力で外部資源を手に入れるだけではなく、異なる文化を持つ組織同士をいかにまとめて成果を出すのかが重要だという。M&Aや組織管理を成功させるにはどんな能力が必要なのだろう?
 組織管理や経営戦略からM&Aを研究
組織管理や経営戦略からM&Aを研究
みなさんはM&A(Merger&Acquisition:合併・買収)に、どのようなイメージを持っていますか? "ハゲタカファンド"に乗っ取られるといった弱肉強食のイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、M&Aは企業がより大きく成長するための有効な戦略の1つです。

私は経営学のなかでも、とくにM&Aのマネジメントについて研究しています。学生時代は企業と資金の動きに興味があって会計学を学びました。それが次第に企業を動かすうえで組織の視点が大切だと考え、経営組織論や戦略論に興味を持つようになりました。きっかけとなったのは、所属していた50人ほどのサークルで会長を任せられたこと。思うように運営ができず、組織を動かすには予算管理やリーダーシップだけではダメだと痛感したのです。そして大学院でマネジメントについて研究するなかで、当時話題になり始めたM&Aに着目しました。
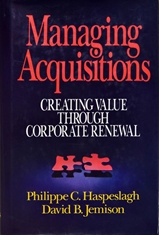
そのころはM&Aの研究といえば、株式や土地、技術などの有形無形の資産から企業の適正な評価額をはじき出す会計的なアプローチが研究の中心でした。組織管理や経営戦略からの研究は少なく、学術書でもほとんど取り上げられていなかった。そんなとき、指導教授から「とにかく読め」と勧められたのが『Managing Acquisitions』という専門書です。そこでは、M&Aで企業を買収することに加えて、組織を統合してから成果を出すまでのマネジメントが分析されていました。この本で、M&Aにおいて全体の流れをマネジメントしていくことの重要性に初めて気づいたのです。
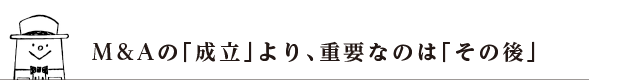 M&Aの「成立」より、重要なのは「その後」
M&Aの「成立」より、重要なのは「その後」
じつは、結婚と M&Aはよく似ています。まず、結婚はいきなりするものではありません。2人が出会ってお付き合いする期間がある。その間に相手の趣味や関心、性格を探り、お互い「イイネ!」となったら結婚するわけです。でも、それで終わりではありません。結婚後も、さまざまなことが起こります。そうした生活を無事やりおおせて、初めて「結婚して良かった」と言えるのです。
M&Aも、企業と企業が出会ってお見合いをして、交渉を経て統合します。しかし、これまでの日本のM&Aの研究はそこまでで、いわば "結婚相談所"止まりでした。相談所が結婚後の生活には関与しないように、M&Aをした後のマネジメントまで考えることはしてこなかったのです。
今でこそM&Aのマネジメントは当たり前の話ですが、当時日本にはその言葉自体がありませんでした。私は2003年にそれまでの研究を『M&Aマネジメントと競争優位』という本にまとめましたが、日本で"M&Aマネジメント"という言葉をタイトルに使ったのは、この本が初めてです。
研究にあたってはいろいろと苦労もあります。まず、M&Aのように大きな交渉ごとは、企業のトップ同士が秘密裏に進めることが多い。また運良くヒアリングができても、ほとんどが守秘義務契約を結ぶため、聞いた話を公表できません。ヒアリングの交渉も企業のトップクラスが対象ですから、コツコツと信頼関係を築いて初めて実現できます。さらに、企業買収に関する法務や財務の知識も必要になるため、研究するにはなかなか手強いテーマとも言えるでしょう。
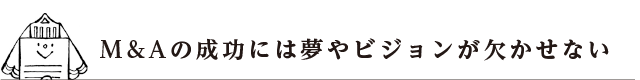 M&Aの成功には夢やビジョンが欠かせない
M&Aの成功には夢やビジョンが欠かせない
さて経営戦略論では、企業の内部にある能力や資源が競争を優位にすると考えます。それは、長年培ってきた技術であったり、社風やブランド力といった目に見えない資源もあります。一方、M&Aは他企業という外部にある資源を活用します。ここでM&Aに成功した企業を分析すると、その内部に"相手企業の資源をうまく取り込んで我が物にする能力"の存在が見えてきます。では、異なる企業文化や歴史を持った企業同士が、M&Aによって大きな力を発揮するためのポイントはどんなところにあるのでしょうか。
いろいろな事例を研究したり、ヒアリングをするなかで見えてきたのが経営者の役割の大きさです。企業が一緒になって、どんな将来が待っているのか? 夢やビジョンを明確に示し、構成員を結束させることができるかどうかが成否を大きく左右します。
私は経営学の理論をよくマンガにたとえて説明します。例えば、人気少年漫画『ONE PIECE』は、主人公のルフィが「海賊王になる」という大きな夢を持って成長していく物語です。さまざまなタイプの海賊団が登場しますが、それぞれがルフィの夢に共感することによって、自分たちの目的も達成できると信じて協力していくのです。

つまりM&Aによって、より豊かな状況になるという未来をいかに提示し、従業員を「その気」にさせるか。M&Aに長けた企業では、どのような手順で成果を上げていくかの「100日プラン」をプログラム化しています。小さな成果を積み上げ、今は苦しくても、2年後や3年後に目標がかなうことが見えると、私たちは頑張れるんですね。
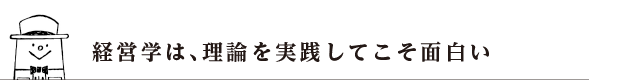 経営学は、理論を実践してこそ面白い
経営学は、理論を実践してこそ面白い
私のゼミでは、経営学を応用したユニークな方法で学生たちを鍛えています。課題はすべてチームごとの対抗戦。いわばアイドルグループ「AKB48」方式です。各自に持ち点を与え課題ごとに競わせると、連帯感から研究をサボらなくなるし、チーム内の協調性も高まります。
じつは、AKBは組織論で見ても面白いんですよ。総選挙に勝つために個人個人が頑張るけれど、公演成功のためには一致団結する。それをプロデューサーの秋元康さんがうまく管理し成長させていく。私も秋元さん的立場で学生を育てているというわけです。
ゼミは研究の実践の場でもあります。やはり、理論は実践してみなければ面白くないし、おかげさまで学生たちのゼミの評価も上がりました。
実践力を磨くために、ゼミ生たちと子ども向けのワークショップも行っています。昨年参加した「奥沢メキシコ・フィエスタ」というイベントでは「製品開発に挑戦しよう」と題して、ソンブレロというメキシコの帽子を作りながらマーケティングを学びました。みんなで帽子をデザインして、キャッチコピーや値段を考えて売るのですが、最初は何もわからなかった子どもたちも体験を通して理論を理解していきます。子どもに一方的に"伝える"のは簡単ですが、本当に"伝わる"には工夫が必要です。いかに子どもたちに経営やマーケティングを理解してもらうか、学生たちは全力で取り組んでいますよ。


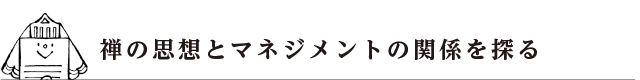 禅の思想とマネジメントの関係を探る
禅の思想とマネジメントの関係を探る
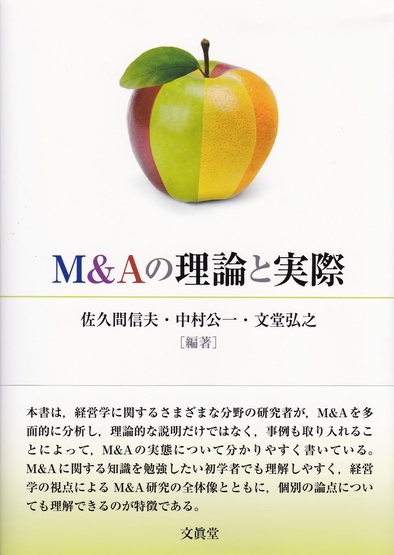
M&Aや経営において、経営者の役割や夢やビジョンが重要だとお話ししました。しかし夢やビジョンをただ漠然と唱えるだけの経営者では人はついていきません。重要なのは、経営者の持つ信念や精神的な支柱となるべき思想、そして過酷な状況を乗り越える「胆力」です。胆力は禅の思想にも通じます。禅では過酷な修行をやり抜くことで1つの境地に達します。
そこで、禅が企業経営にどんな影響を与えているのか、それを取り入れることで企業がどう変わるのか、という研究を始めています。例えば、京セラや第二電電(現KDDI)を創業し、JAL再生に陣頭指揮をふるった稲盛和夫さんは、65歳で得度され、その経営には禅の思想が強く反映されているといわれます。Appleの創設者、スティーブ・ジョブズが禅に傾倒していたことも広く知られており、彼の思想は同社の製品開発に明らかに現れています。このように、禅の思想を取り入れた成長企業は少なくないのですが、その思想とマネジメントの関係性はこれまできちんと研究されてきませんでした。
グローバリゼーションが進むなか、今後も市場競争はますます激しくなり、業界上位の企業も下位の企業を取り込まないと成長できなくなってくるでしょう。まだまだM&Aは増えてくると思います。そうしたなか、禅とマネジメントというテーマが確立できれば、M&Aの分野でも駒澤大学らしいユニークな提案ができるのではないかと考えています。

- 中村 公一教授
- 立教大学経済学部卒業。横浜国立大学大学院国際開発研究科博士後期課程修了。博士(学術)。2001年より駒澤大学経営学部で教鞭を執る。専門は経営戦略論、組織間関係論。M&Aマネジメント。著書に『M&Aマネジメントと競争優位』・「M&Aの理論と実際」(編著)ほか。日本マネジメント学会常任理事。学内では管弦楽団と漫画倶楽部の顧問を務める。
相手の文化や歴史を理解するには、様々な書物を読み解くことが近道になることも・・・
ということで次回は「日本の出版文化のおもしろさ」にタスキを繋ぎます!
- 駒澤大学ラボ駅伝とは・・・
- 「ラボ」はラボラトリー(laboratory)の略で、研究室という意味を持ちます。駒澤大学で行われている研究を駅伝競走になぞらえ、リレー形式で紹介する連載メディアです。創造的でユニークな研究を通して見える「駒大の魅力」をお伝えします。
関連記事 - 「ラボ駅伝」カテゴリーの新着記事
 2025.03.19
2025.03.19
 2025.02.03
2025.02.03
第32区 仲田資季准教授『プラズマの渦と流れの物理と数理』
 2024.04.10
2024.04.10
第31区 近衞典子教授『上田秋成から見る近世文学』
 2024.03.05
2024.03.05